

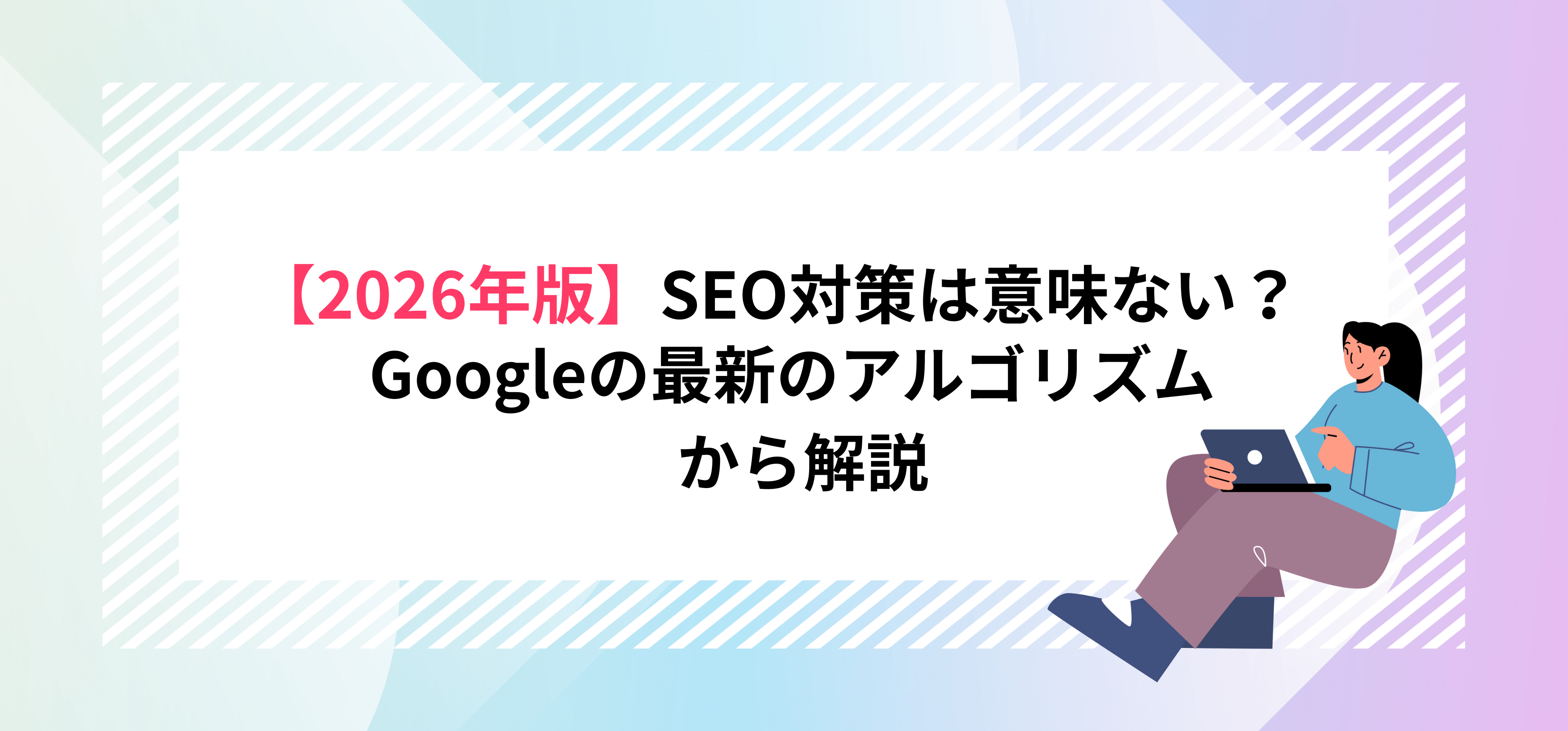
« RÉFÉRENCEMENT ». Je pense que c'est un mot que j'ai déjà entendu quelque part.
Les personnes qui créent des sites Web et rédigent des articles sont familières, n'est-ce pas ?
Le référencement indique des mesures visant à afficher le site de l'entreprise plus haut sur les moteurs de recherche, et diverses mesures efficaces sont appelées mesures de référencement.
Cette fois, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles on dit que de telles mesures de référencement n'ont aucun sens et les raisons pour en faire des mesures de référencement significatives.

Tout d'abord, le référencement signifie optimisation pour les moteurs de recherche et indique des mesures visant à afficher des sites, des articles, etc. à un niveau supérieur sur les moteurs de recherche tels que Google et Yahoo.
Les mesures de référencement comprennent non seulement la production de contenu de haute qualité requis par les utilisateurs, mais également l'optimisation des éléments techniques tels que le code et la structure.
Les mesures de référencement ont pour but de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement leurs propres sites et articles, en d'autres termes, d'augmenter le nombre d'accès.
S'il est affiché sur la première page des résultats de recherche, voire dans le top 3, sur les moteurs de recherche tels que Google et Yahoo, le nombre d'accès augmente.
Cependant, même avec des mesures de référencement, l'algorithme de recherche de Google change d'année en année, il est donc difficile d'être évalué sans créer d'originalité ou le contenu le plus récent.
Comprendre le type d'informations que les utilisateurs recherchent et les termes de recherche qu'ils utilisent pour rechercher un site est un point important des mesures de référencement.
Article de référence :https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide
Article de référence :https://www.japan-feux-france.com/column/about-seo

Comme il existe d'innombrables sites et articles sur le Web, certaines personnes pensent probablement que les mesures de référencement n'ont pas beaucoup de sens à l'ère d'Internet.
Cependant, si vous avez la bonne stratégie et la bonne continuation, les mesures de référencement seront significatives.
Nous allons résumer ici certaines des raisons pour lesquelles on dit que les mesures de référencement n'ont aucun sens.
Étant donné que les mesures de référencement produisent des résultats basés sur des stratégies sur une longue période, les résultats des initiatives à court terme ne sont pas souvent visibles.
En gros, cela prend environ six mois entre le lancement du site et le démarrage des mesures de référencement.
En effet, pour évaluer avec précision un site comme étant fiable et faisant autorité, une certaine quantité d'informations et de données est requise.
La raison pour laquelle on dit que les mesures de référencement n'ont pas de sens a la particularité que les effets n'apparaissent pas immédiatement.
L'algorithme de recherche de Google est mis à jour régulièrement et les résultats des mesures de référencement fluctuent également en fonction de l'algorithme.
Les normes relatives aux algorithmes changent d'année en année afin de fournir des informations plus appropriées aux utilisateurs.
Par conséquent, les sites et les articles qui étaient affichés en haut de la page peuvent également chuter dans le classement des résultats de recherche en raison de modifications apportées à l'algorithme.
Récemment, les points d'expérience ont pris de l'importance et les évaluations de la fiabilité et de l'expertise ont tendance à augmenter.
Bien que l'on dise que les mesures de référencement n'ont aucun sens, de nombreuses entreprises y travaillent.
Par conséquent, il est très difficile d'améliorer le classement des écrans, en particulier dans les domaines où la concurrence est intense.
S'il s'agit d'un domaine de niche, il est facile de se différencier, mais dans un domaine où les conflits concurrentiels sont intenses, en plus de la fiabilité et de l'expertise, il est nécessaire d'être supérieur aux autres contenus en raison de leur contenu unique.
Ces dernières années, en raison de la diffusion d'IA génératives telles que ChatGPT, la composition « chaque recherche = recherche Google » est en train de changer.
Au lieu de saisir des mots clés dans les moteurs de recherche, les utilisateurs posent de plus en plus de questions directement à l'IA et obtiennent des réponses qui résument les principaux points. En conséquence, il existe un phénomène dans lequel le taux de clics des résultats de recherche ciblés par les mesures de référencement classiques baisse de façon drastique.
Néanmoins, les moteurs de recherche n'ont pas complètement disparu et de nombreux utilisateurs utilisent toujours Google pour obtenir des informations très fiables, et la valeur en tant que destination de référence pour les données reste la même.
Même à l'ère de l'IA, la création d'un « site performant en termes de recherche » est toujours efficace pour obtenir un accès continu. Le référencement doit être considéré comme quelque chose qui « évolue » plutôt que comme quelque chose qui « prend fin ».
L'algorithme de Google évolue d'année en année, et la tendance se renforce d'année en année lorsque « la satisfaction des utilisateurs » est mise en avant sur les pages qui incluent simplement des mots clés ou un contenu qui renforce l'extérieur avec des liens.
Par exemple, l'ensemble de l'expérience utilisateur (UX) est devenu central dans l'axe d'évaluation, comme la vitesse d'affichage, la compatibilité mobile, la configuration facile à lire et la fourniture d'informations uniques.
Par conséquent, quelle que soit la technique d'optimisation du référencement, si le contenu de la page est difficile à lire ou si les informations attendues ne peuvent pas être trouvées, il devient difficile de monter dans les classements de recherche.
L'une des raisons est que les gens pensent que « le référencement n'a plus de sens » en réponse à la tendance actuelle selon laquelle la « satisfaction humaine » est plus importante que les astuces techniques.
Le moteur de recherche de Google met l'accent sur la « recherche sémantique (recherche basée sur la sémantique) », qui comprend le contexte et le sens, plutôt que sur la correspondance des mots comme c'était le cas auparavant.
Par conséquent, il est devenu difficile d'afficher les premières positions sur les pages qui ne couvrent que des mots clés, et il existe une forte tendance à évaluer le contenu qui capture avec précision les intentions de recherche.
Par conséquent, il est devenu difficile de produire des résultats avec les seules « techniques de référencement » classiques, et le nombre de personnes qui pensent que « le référencement n'a plus de sens » augmente.
Cependant, cela signifie également que des « informations vraiment précieuses » ont été sélectionnées à mesure que la précision de la recherche augmentait.
En d'autres termes, si un contenu de haute qualité peut être fourni, on peut dire que la possibilité d'obtenir des résultats au-delà des compétences techniques s'élargit plutôt.
Afin d'améliorer la fiabilité des résultats de recherche, Google a décidé d'accorder de l'importance à « qui envoie ces informations ».
Par conséquent, il existe une tendance à un traitement préférentiel pour les sites fiables dans tous les domaines, tels que les bureaux gouvernementaux, les universités, les grandes entreprises et les médias faisant autorité.
Dans cette situation, quelle que soit la qualité du contenu créé par un individu ou un site de petite ou moyenne taille, il est parfois difficile de se hisser dans les premières positions de recherche, ce qui donne aux internautes l'impression que « le référencement est terminé ».
Cependant, bien que la fiabilité ne puisse pas être construite du jour au lendemain, il est possible d'augmenter progressivement la valeur du domaine grâce à la diffusion continue des informations, à l'acquisition de backlinks et à l'assistance des utilisateurs.
Les mesures de référencement dans une perspective à long terme sont des moyens efficaces qui peuvent conduire à des résultats significatifs dès maintenant.
Afin de produire des résultats avec le référencement, un contenu utilisant des informations originales, des données et des connaissances spécialisées est désormais requis.
Par conséquent, il est impossible de battre la concurrence avec des articles qui peuvent être facilement externalisés, et les entreprises et les créateurs peuvent avoir l'impression qu' « il est difficile de produire un effet à la hauteur du coût en temps et en argent ».
De plus, étant donné que de nombreux processus sont nécessaires, tels que la recherche, la configuration, l'édition et la présentation des preuves pour viser des positions de recherche plus élevées, on pense que « les obstacles à l'entrée sont plus importants » qu'auparavant.
Le contenu créé grâce à un investissement solide est très apprécié et constitue un actif à long terme. Ce n'est pas que les coûts sont élevés = inutiles ; cela doit plutôt être considéré comme un changement dans une structure où « vous n'êtes récompensé que pour ce que vous faites ».
Après avoir mis en œuvre des mesures de référencement, examinons également les cas courants où il n'y a aucun effet ou où les gens abandonnent sans résultat.
Un malentendu courant chez les personnes qui viennent de commencer à prendre des mesures de référencement est de s'attendre à ce que « le classement des recherches augmente en quelques semaines et que l'accès augmente immédiatement ».
Mais en réalité, Google met du temps à évaluer votre site ou votre contenu. En particulier dans le cas des nouveaux domaines, l'indexation est retardée et la fiabilité du domaine lui-même est faible. Il n'est donc pas rare que les résultats prennent des mois à six mois ou plus.
C'est pourquoi il est inutile de juger le référencement comme « dénué de sens » au motif que les résultats ne sont pas publiés en peu de temps.
Le référencement est une méthode de marketing qui permet d'obtenir des résultats à moyen et long terme, et une amélioration et une continuité constantes sont la clé du succès. L'attitude consistant à travailler régulièrement sans être impatient est apparue plus tard comme une grande différence.
Il existe également des cas courants où des articles sont produits en série sans réfléchir sérieusement à la sélection ou à la structure des mots clés, en pensant « de toute façon, si nous augmentons le nombre d'articles, le classement dans les recherches augmentera ».
Cependant, dans le référencement actuel, le simple fait d'augmenter le nombre de contenus n'est pas efficace, et il existe même un risque que des articles de mauvaise qualité réduisent l'évaluation globale du site. Étant donné que Google évalue le contenu qui correspond exactement à l'intention de recherche de l'utilisateur, cela ne s'applique pas aux articles dont le contenu est médiocre ou qui répètent des informations similaires.
Ce qui importe avant tout, c'est de savoir « si le contenu est réellement utile aux utilisateurs ». En augmentant le degré de perfection de chaque article et en tenant compte du choix du thème et de la structure qui correspondent à l'intention de recherche, il est possible de produire régulièrement des résultats, même avec un petit nombre d'articles.
La quantité est importante, mais en mettant l'accent sur la qualité, vous devriez être en mesure de ressentir clairement la valeur du référencement.
Le référencement est une mesure qui produit des résultats en « accumulant les améliorations ». Néanmoins, il est impossible de déterminer ce qui était bon et ce qui ne l'était pas si vous laissez l'article publié et ne vérifiez pas les changements de classement ou la présence ou l'absence de flux entrants.
Si vous continuez à ne pas voir de résultats, votre motivation diminuera et il sera facile de mal comprendre que « le référencement n'a aucun sens ».
En réalité, en analysant régulièrement l'évolution des classements de recherche, des taux de clics, du temps passé, etc., de nombreux indices d'amélioration peuvent être trouvés, et la tendance diffère également en fonction de chaque requête de recherche.
Il est possible de revoir votre stratégie en sachant où se situe le contenu de votre entreprise dans les mots clés cibles et quelles sont les différences par rapport à la concurrence. Si vous ne regardez pas les chiffres, vous n'obtiendrez aucun résultat. Faire face aux données est la première étape d'un référencement réussi.
Pour obtenir des résultats avec le référencement, une « raison à choisir par les utilisateurs de recherche » est nécessaire. Toutefois, si vous créez un article avec un contenu et une structure similaires à ceux d'un site concurrent qui a déjà été affiché en haut de la page, il sera traité comme une « information qui ne semble pas bonne » à la fois pour Google et pour les utilisateurs, et il sera difficile de se hisser dans les premières positions.
Il est efficace d'intégrer des éléments uniques tels que des perspectives uniques, des expériences spécifiques, des données d'enquête et des illustrations pour différencier les concurrents.
Au lieu de simplement compiler des informations, il montre clairement « pourquoi cette page vaut la peine d'être lue », ce qui en fait un contenu choisi à la fois par les utilisateurs et les moteurs de recherche. L'ingéniosité pour ne pas être enterrée dans d'autres articles est la clé du référencement.
Dans de nombreux cas, les gens pensent que « le référencement devrait être laissé à des experts » et s'en prennent à des rédacteurs bon marché. Cependant, pour atteindre des positions de recherche plus élevées, il ne suffit pas de satisfaire au nombre de caractères, et il est nécessaire de comprendre l'intention de recherche, l'expertise, la structure des phrases et de tenir compte de la psychologie de l'utilisateur.
Il s'agit d'un cas où des articles de mauvaise qualité sont produits en série à la suite d'une sous-traitance alors que les instructions de sélection des traders et des rédacteurs sont vagues, ce qui entraîne une déception lorsque cela ne donne pas de résultats et que le référencement n'a aucun sens.
Le recours à l'externalisation en soi n'est pas un mauvais choix, mais plutôt que de choisir de manière appropriée, il est nécessaire de communiquer clairement les politiques et les objectifs de l'entreprise et de gérer fermement le plan de structure et la stratégie de mots clés.
Afin de produire des articles de haute qualité, l'implication des donneurs d'ordre est également essentielle. L'externalisation n'est qu'un moyen, et le fait de savoir que c'est à vous d'élaborer une stratégie est la ligne de démarcation du succès du référencement.
Le référencement est à l'origine un mécanisme destiné aux utilisateurs, mais il peut aussi leur faire penser que c'est ennuyeux de viser un rang plus élevé.
Il est important d'inclure les mots clés de manière appropriée comme base pour les mesures de référencement, mais une utilisation excessive est contre-productive.
Par exemple, les phrases où les mêmes mots clés sont répétés de manière anormale sont extrêmement difficiles à lire pour les lecteurs et donnent une impression mécanique. Il n'est pas rare que l'insertion excessive de mots clés soit l'une des raisons pour lesquelles les gens pensent que « cette page est un peu difficile à lire ».
L'algorithme de Google est déjà strict contre ce type de « spam par mots clés », et l'accent est mis sur les phrases naturelles et sur la facilité de lecture pour les lecteurs.
En d'autres termes, au lieu d'intégrer des mots clés pour le référencement, l'essentiel est de « les utiliser dans un contexte significatif pour les lecteurs », et c'est un point qui continuera d'être évalué à l'avenir.
Dans le passé, on a constaté une augmentation du contenu très long dépassant les 10 000 caractères par article, en raison de l'idée que « plus vous restez longtemps sur une page, plus elle est évaluée ». Cependant, dans de nombreux cas, les utilisateurs ne peuvent pas arriver rapidement à la conclusion qu'ils souhaitent connaître, et la lecture devient un problème et ils partent.
Bien entendu, il est inévitable qu'un article soit publié longtemps après avoir inclus les informations nécessaires, mais beaucoup d'informations ne signifie pas nécessairement qu'il est aimable et risque de donner une impression plutôt redondante.
Cependant, Google a récemment accordé une meilleure évaluation à la « capacité des utilisateurs à résoudre des problèmes », et la fourniture d'informations simples et précises est requise en fonction des requêtes de recherche.
Même s'il s'agit d'une longue phrase, il serait utile que la structure soit significative, mais le contenu qui a été étiré inutilement est considéré comme une « production excessive » pour le référencement, et les utilisateurs ont tendance à ne pas l'aimer.
Si la plupart des articles affichés en haut des résultats de recherche ne sont que des articles d'introduction « avec des projets d'affiliation », les utilisateurs deviennent progressivement sensibles à cette tendance. Si vous pensez « s'agit-il encore d'une publicité » ou « après tout, seuls les projets publicitaires sont recommandés », la fiabilité et le niveau de satisfaction à l'égard de l'article lui-même diminueront considérablement.
Bien sûr, ce n'est pas que les affiliés soient mauvais, mais si les produits et services introduits ne résolvent pas vraiment les problèmes des utilisateurs, ils porteront atteinte à la confiance du contenu.
Dans le futur référencement, « la fourniture d'informations honnêtes », « des évaluations basées sur l'expérience » et des « motifs de comparaison et de sélection » seront davantage nécessaires. Structurer du point de vue du lecteur d'abord plutôt que d'avoir un projet sera à terme un raccourci vers le succès en matière de référencement.
Le référencement est une arme majeure lorsque vous souhaitez obtenir des résultats, mais il est également vrai qu'il existe des cas où il vaut mieux ne pas prioriser le référencement en fonction de certains genres.
Le référencement n'est pas une priorité absolue pour tous les genres.
En particulier, les informations, les divertissements et les contenus très tendances mettant l'accent sur les visuels sont parfaitement compatibles avec les réseaux sociaux et les vidéos. Par exemple, il existe une tendance à ce que de plus en plus d'utilisateurs recherchent « comment se maquiller », « chorégraphie de danse », « vlogs de voyage », etc. via Instagram, TikTok et YouTube plutôt que de rechercher.
Dans de tels genres, plutôt que de consacrer des efforts au référencement, il est fort possible que l'augmentation du pouvoir de diffusion sur les SNS ou la création d'un attrait visuel à l'aide de vidéos aboutissent à des résultats en peu de temps.
Il n'est pas nécessaire d'ignorer complètement le référencement, mais pour utiliser efficacement des ressources limitées, il est important de hiérarchiser les priorités en fonction de « l'endroit où les utilisateurs recherchent actuellement des informations ».
Le référencement est à l'origine une mesure visant à obtenir l'effet d'attirer des clients sur le moyen et long terme. La publication de contenu n'a pas nécessairement un effet immédiat, et il faut un certain temps pour qu'il soit évalué par Google et reflété dans les résultats de recherche.
Par conséquent, s'il existe des objectifs à court terme tels que « Je souhaite augmenter mes ventes dans un délai d'un mois » ou « Je souhaite doubler l'accès d'ici la fin du mois », il est inefficace de définir le référencement comme politique principale.
Dans de tels cas, les mesures ayant un effet immédiat, telles que les publicités sur les réseaux sociaux, les annonces publicitaires et le marketing par e-mail, doivent d'abord être examinées.
Le référencement doit être abordé du point de vue de « quelque chose à cultiver », et penser séparément des mesures à court terme est la clé du succès.
Dans le cas de thèmes trop spécialisés, le nombre de recherches (volume de recherche) peut être extrêmement faible au départ.
Par exemple, dans de nombreux cas, on ne peut guère s'attendre à un accès en soi, quel que soit le niveau d'affichage du classement, par exemple « méthodes de maintenance pour les pièces d'une machine industrielle spécifique » ou « explications sur les douanes limitées à une certaine région ».
Dans de tels cas, même si du temps et des efforts sont consacrés au référencement, le rendement est faible et cela devient une « mesure déraisonnable ».
Il existe plutôt des cas où la transmission par SNS avec une cible claire, le partage d'informations au sein de communautés spécialisées et une approche directe par e-mail ou par le biais des ventes sont plus susceptibles de donner des résultats.
Comme il n'est pas recherché, cela ne signifie pas qu'il n'a aucun sens, et une combinaison avec d'autres canaux ou une transmission avec une plus grande précision est nécessaire.
Jusqu'à présent, on a dit à de nombreuses reprises que le référencement n'avait aucun sens, mais il n'a pas changé et a eu un impact important, et il est vrai que les grandes entreprises travaillent également sérieusement sur le référencement.
Ici, voyons également pourquoi le référencement continuera d'être une arme puissante.
Il est vrai que le comportement de recherche a changé en raison de la propagation de l'IA et des SNS, mais malgré tout, le comportement de recherche consistant à « rechercher des informations de sa propre volonté » n'a pas disparu.
Les utilisateurs qui ont clairement ce qu'ils veulent rechercher continueront à utiliser les moteurs de recherche pour essayer d'obtenir les informations dont ils ont besoin. En particulier, la recherche reste la méthode la plus courante pour comparer et examiner des produits et services, obtenir des connaissances spécialisées et confirmer des informations hautement fiables.
En d'autres termes, le référencement continuera d'avoir un sens tant qu'il sera recherché. Étant donné que les utilisateurs de recherche ont de fortes intentions, telles que « Je veux savoir maintenant » et « Je veux acheter tout de suite », le référencement, qui peut aborder ces utilisateurs, continuera à fonctionner comme un outil de marketing efficace à l'avenir.
Les moteurs de recherche, à commencer par Google, évoluent d'année en année. Désormais, le poids est accordé non seulement aux mots clés simples et au nombre de backlinks, mais également aux algorithmes qui évaluent le contenu, la fiabilité et la satisfaction des utilisateurs, et il n'est pas difficile d'imaginer que cette tendance continuera à se renforcer à l'avenir.
En d'autres termes, nous préparons un environnement dans lequel il sera plus facile d'évaluer plus correctement le contenu de haute qualité créé pour les utilisateurs. Il ne s'agit pas d'un référencement naturel banal, et nous nous rapprochons d'un système où « les informations à valeur essentielle » arrivent naturellement en tête.
L'évolution des moteurs de recherche est plutôt un facteur favorable pour ceux qui diffusent sincèrement des informations, et on peut dire que c'est la raison pour laquelle le référencement continuera d'être une arme puissante à l'avenir.
Plutôt que d'être abordé seul, le référencement démontre un effet de synergie significatif en le combinant avec d'autres mesures marketing et activités commerciales.
Par exemple, en le liant à des communiqués de presse, à des sujets de réseaux sociaux, à des événements réels, à des vidéos YouTube, etc., il est plus facile d'obtenir des backlinks naturels et des citations (mentions sur d'autres sites et SNS), et les évaluations des moteurs de recherche augmentent également.
De plus, à mesure que la valeur de marque du produit/service augmente, le nombre de fois que les utilisateurs effectuent des recherches volontaires augmente également et le flux vers le référencement est également renforcé.
Ainsi, le référencement n'est pas « quelque chose qui doit être fait séparément », mais constitue une base pour obtenir de meilleurs résultats en établissant des liens avec des activités telles que les relations publiques, l'image de marque, les réseaux sociaux et la publicité.
L'une des plus grandes forces du référencement est que si vous publiez un contenu de haute qualité et que vous obtenez un certain niveau d'évaluation, vous pouvez obtenir un accès continu sans dépenser de frais de publicité.
En particulier, les utilisateurs des moteurs de recherche ont clairement l'intention de « rencontrer des problèmes » ou de « chercher des réponses », et s'ils peuvent répondre à ces besoins, ils peuvent acquérir des clients de très haute qualité.
Par exemple, lorsque les utilisateurs ont des préoccupations ou des problèmes, tels que « des maux de dos, des étirements » ou « comment déposer une déclaration de revenus », on peut s'attendre à un afflux continu si ce contenu est consulté.
En tant que mécanisme visant à attirer naturellement ces « utilisateurs très motivés », le référencement continuera d'être un canal extrêmement efficace pour attirer des clients à l'avenir. Comme l'effet ne tombe pas à zéro en même temps que l'arrêt du placement de la publicité, il peut également s'agir d'un actif à long terme.

Les mesures de référencement mettent du temps à obtenir des résultats, mais j'ai mentionné que si vous continuez avec la bonne stratégie, les résultats apparaîtront.
Ici, je vais expliquer les derniers algorithmes de recherche de Google à garder à l'esprit afin de mettre en œuvre des mesures de référencement significatives.
Afin de mettre en œuvre des mesures de référencement efficaces, il est essentiel de comprendre l'algorithme de recherche en constante évolution de Google.
L'algorithme de Google indique des normes et des règles pour déterminer le classement d'affichage des résultats de recherche, et des mises à jour sont effectuées régulièrement.
Comment devons-nous suivre le rythme des algorithmes qui fluctuent en fonction des besoins des utilisateurs et de l'évolution des temps ?
Nous vous recommandons de suivre les directives officielles et les documents fournis par Google.
Surtout, le « Google SEO Starter Guide » contient des informations complètes sur les bases du référencement.
Étant donné que les principes des algorithmes et des mesures de référencement spécifiques sont également détaillés, il est facile à utiliser comme matériel de référence.
L'algorithme de Google est régulièrement mis à jour, donc même si vous le maîtrisez une fois, il fluctuera en fonction de la mise à jour.
Par conséquent, la saisie des dernières informations sur les mises à jour conduit à des mesures de référencement significatives.
En particulier, les mises à jour de base sont des mises à jour dans lesquelles le système est fondamentalement révisé, alors ne les manquez pas.
Assurez-vous de vérifier les informations de mise à jour annoncées sur le réseau social et le site Web officiels de Google.
Pour ressentir les changements dans l'algorithme de Google, tester et analyser les politiques de votre propre site est une méthode facile à comprendre.
Des mots clés spécifiques sont définis et un contenu contenant des mesures de référencement appliquées est fourni.
Utilisez ensuite la console de recherche Google pour effectuer des analyses régulières.
En testant les mesures, vous pouvez déterminer quels types de mesures sont efficaces et combien de temps il faudra pour que les effets se fassent sentir.
L'ampleur des mises à jour des algorithmes varie en fonction du contenu. C'est donc une bonne idée de constater de première main leur impact sur les mesures de référencement.

J'ai appris les mesures de référencement en gérant des sites Web et en écrivant des articles pour des étudiants universitaires qui publient des articles sur la recherche d'emploi, les stages, les études à l'étranger, les emplois à temps partiel, etc.
Je me souviens que même après avoir pris diverses mesures de référencement sur le site qui venait d'être lancé, il n'y avait aucun résultat immédiat.
En particulier, il est difficile de terminer un article avec un contenu affiché en haut de la page pour les mots clés de recherche où les concurrents sont nombreux.
Par conséquent, je recherchais des mots-clés de niche et j'écrivais des expériences réelles en détail.
Après environ six mois à un an, les mesures conçues pour améliorer l'affichage, telles que les mots clés et les codes, commenceront à porter leurs fruits, et le nombre d'articles affichés sur la première page des résultats de recherche augmentera.
Comme les résultats ne sont pas immédiatement visibles, il est facile de dire que les mesures de référencement n'ont aucun sens, mais en poursuivant la bonne stratégie et en la mettant à jour, il s'agit d'une contre-mesure SEO significative.

Cette fois, j'ai expliqué pourquoi on dit que les mesures de référencement n'ont aucun sens et comment répondre aux mises à jour de l'algorithme de Google.
On dit que les mesures de référencement n'ont aucun sens car elles ne fonctionnent pas tout de suite et il y a beaucoup de concurrence.
Cependant, si l'algorithme de Google est supprimé et que plusieurs mesures sont maintenues, les effets peuvent souvent être observés au bout de six mois environ. Il s'agit donc d'une mesure de référencement significative.
